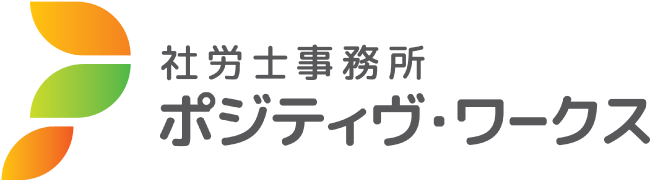こんにちは。ポジティヴ・ワークス代表 社会保険労務士の出町です。
今回は、令和7年6月1日に施行された「改正労働安全衛生規則」について、特に「職場における熱中症対策の強化」に焦点を当てて、社会保険労務士として重要なポイントを解説いたします。
年々深刻化する夏の暑さから従業員を守るため、事業主の皆さまは本改正の内容をしっかりと理解し、適切な対策を講じることが求められます。
なぜ今、熱中症対策の強化が必要なのか?
厚生労働省のデータを見ると、職場における熱中症による死亡災害は、過去2年連続で30人レベルと高止まりしています。熱中症は他の労働災害と比較して死亡に至る割合が約5~6倍と非常に高く、特に屋外作業での死亡者が約7割を占めているため、気候変動の影響によるさらなる増加が懸念されています。
これらの死亡災害のほとんどが、「初期症状の放置」や「対応の遅れ」が原因とされています。具体的には、「発見の遅れ(重篤化した状態で発見されるケースが78件)」や「異常時の対応の不備(医療機関に搬送しないケースが41件)」といった分析結果が出ています。

このような状況を受け、今回の改正では、熱中症による重篤化を防ぐための具体的な対策が事業者に義務付けられることになります。
改正労働安全衛生規則の基本的な考え方
今回の改正の基本的な考え方は、以下の3つのステップで熱中症から労働者を守ることにあります。
- 見つける: 作業員の様子がおかしいなど、熱中症の初期症状を早期に発見すること。
- 判断する: 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合、医療機関への搬送や救急隊要請など、迅速かつ的確な判断をすること。
- 対処する: 救急車が到着するまでの間、作業着を脱がせて水をかけ全身を急速冷却するなど、適切な応急処置を行うこと。
これらのステップを現場の実態に即して具体的に実施するための対応が求められます。
事業者に義務付けられる具体的な対策
熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
1. 体制整備と関係者への周知
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備と関係作業者への周知が必要です。
単に報告を待つだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイスの活用、双方向での定期連絡などを通じて、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握する努力が求められます。
2. 手順の作成と関係者への周知
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断ができるよう、以下の手順を作成し、関係作業者へ周知する必要があります。
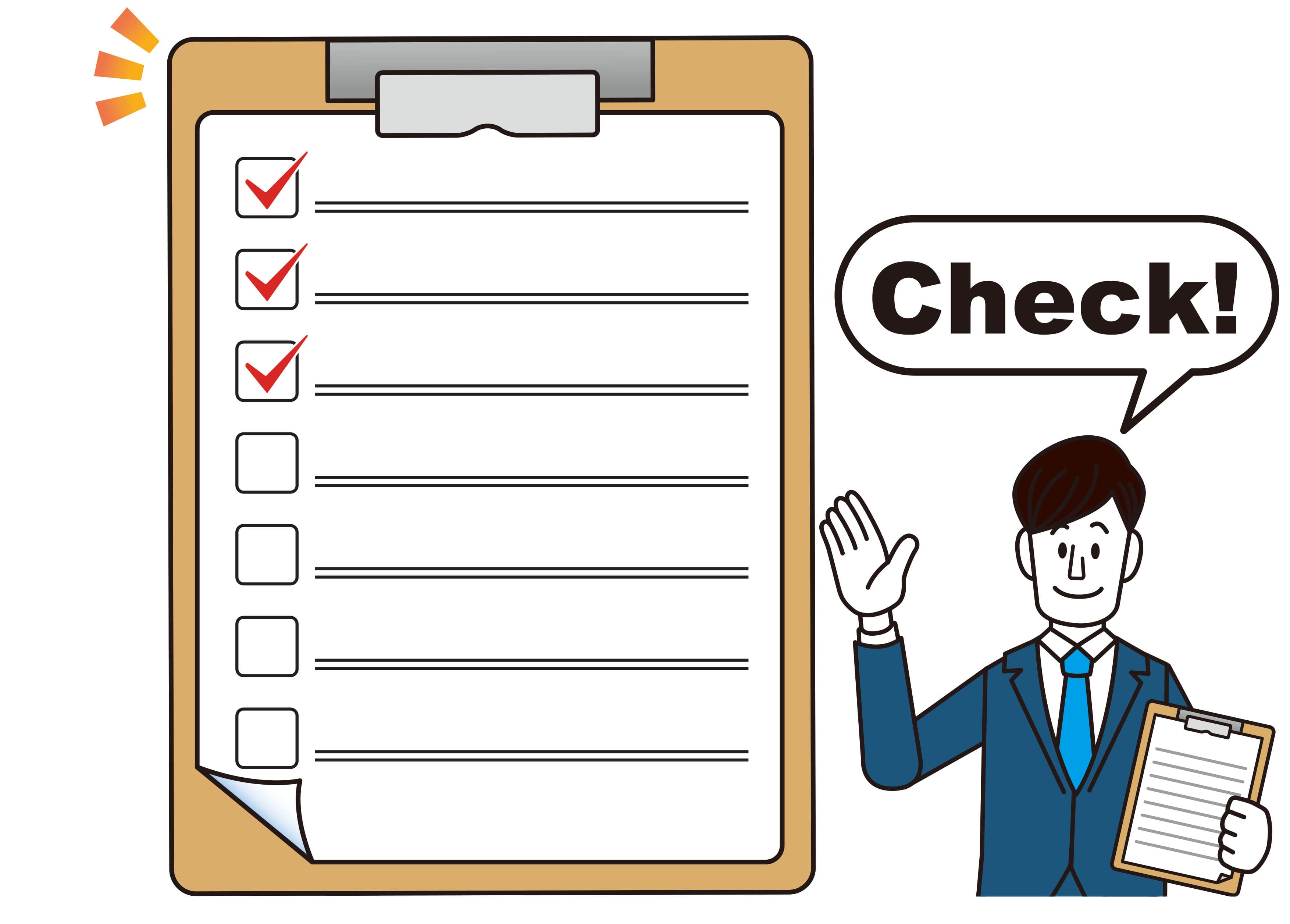
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地。
- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順。
厚生労働省からは参考となるフロー図も提示されていますが、これはあくまで参考例であり、各現場の実情に合わせた内容にすることが重要です。
対象となる作業環境
この対策が必要となる対象は、「WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
WBGT値(暑さ指数)の活用と熱中症予防対策
「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づき、WBGT値(暑さ指数)の活用が重要です。WBGT値とは、暑熱環境による熱ストレスを評価する暑さ指数であり、日本産業規格JIS Z 8504を参考に、実際の作業現場で測定・把握することが推奨されています。
WBGT基準値を超える場合には、以下の対策を検討しましょう。
- 冷房などにより作業場所のWBGT値を低減する。
- 身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更する。
- WBGT基準値より低いWBGT値である作業場所での作業に変更する。
それでも基準値を超える場合には、「第2熱中症予防対策」として以下の取り組みが必要です。
1. 作業環境管理
- WBGT値の低減等: 屋外作業場所では、直射日光や照り返しを遮る簡易な屋根などを設置すること。
- 休憩場所の整備等: 高温多湿作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所や日陰などの涼しい休憩場所を設けること。
2. 作業管理
- 作業時間の短縮等。
- 暑熱順化: 高温多湿作業に従事させる場合、計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましい。
- 水分および塩分の摂取: 自覚症状の有無にかかわらず、作業前後の摂取および作業中の定期的な摂取を指導すること。
- 服装等: 熱を吸収・保温しにくい、透湿性・通気性の良い服装を着用させること。
- 作業中の巡視。
3. 健康管理
- 健康診断結果に基づく対応等。
- 日常の健康管理等: 睡眠不足、体調不良、飲酒、朝食未摂取などが熱中症発症に影響を与えることに留意し、日常の健康管理指導や健康相談を行うこと。
- 労働者の健康状態の確認。
- 身体の状況の確認。

4. 労働衛生教育
作業を管理する者および労働者に対して、以下の事項について労働衛生教育を行うことが重要です。
- 熱中症の症状
- 熱中症の予防方法
- 緊急時の救急処置
- 熱中症の事例
「いつもと違う」に気づくことの重要性
熱中症の初期症状は多岐にわたります。
「手足がつる」「イライラしている」「立ちくらみ・めまい」「何となく体調が悪い」「吐き気」「すぐに疲れる」といった自覚症状だけでなく、
「呼びかけに反応しない」「汗のかき方がおかしい(止まらない、または出ない)」「ボーッとしている」「フラフラしている」など、周囲から見て「いつもと違う」と感じる変化にも注意が必要です。
これらの異変に気づいたら、すぐに周囲の人や現場管理者に申し出る、あるいは管理者から声をかけるといった対応が命を守ることに繋がります。

まとめ
令和7年6月1日の改正労働安全衛生規則の施行により、職場における熱中症対策は一層強化されます。事業主の皆さまには、WBGT値の活用、作業環境・作業・健康管理の徹底、そして労働衛生教育の実施を通じて、従業員の命と健康を守るための具体的な取り組みが求められます。
今回の改正を機に、貴社の熱中症対策を見直し、より安全で健康的な職場環境の整備を進めていきましょう。ご不明な点や具体的な対策についてのご相談がありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。